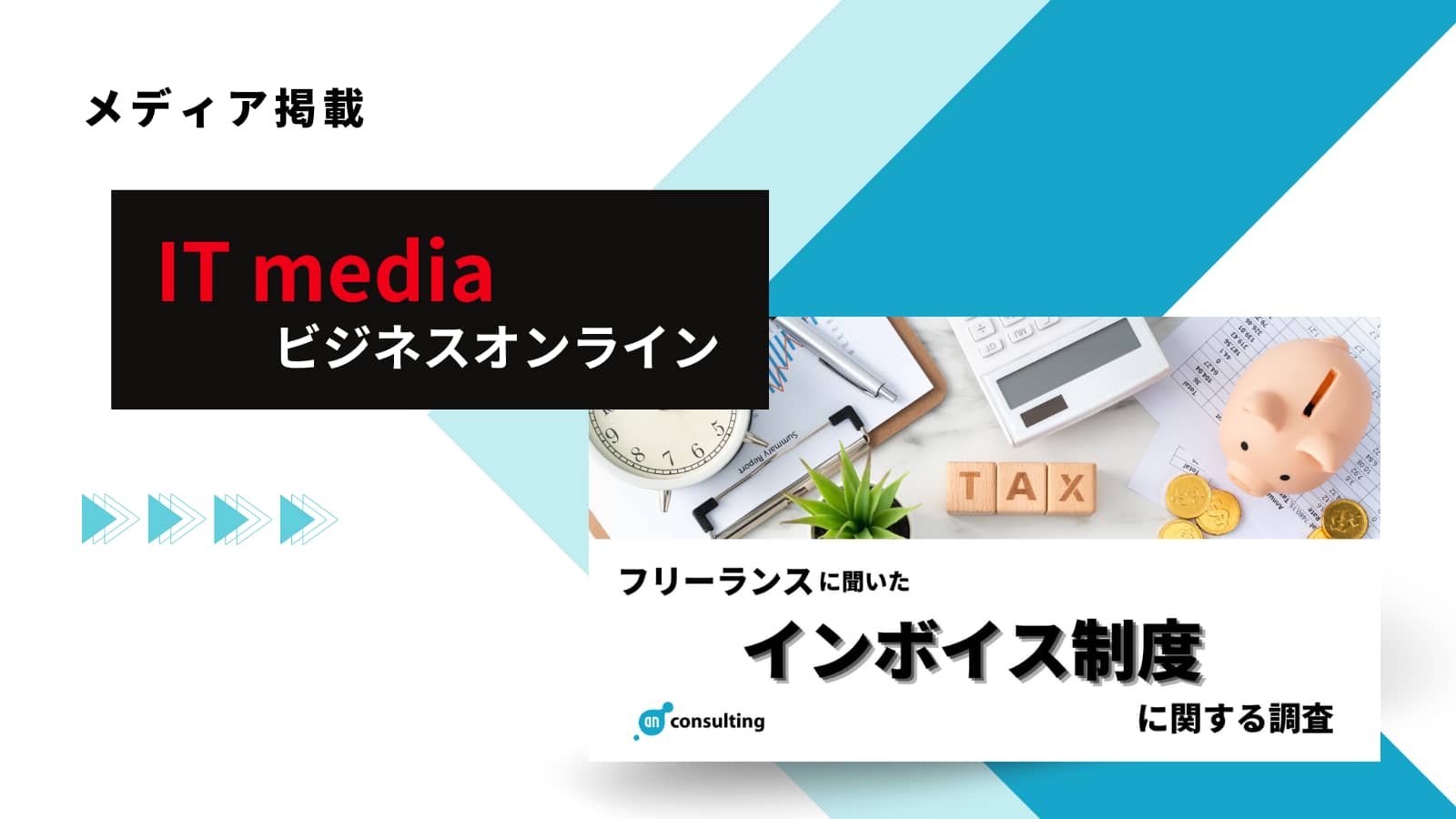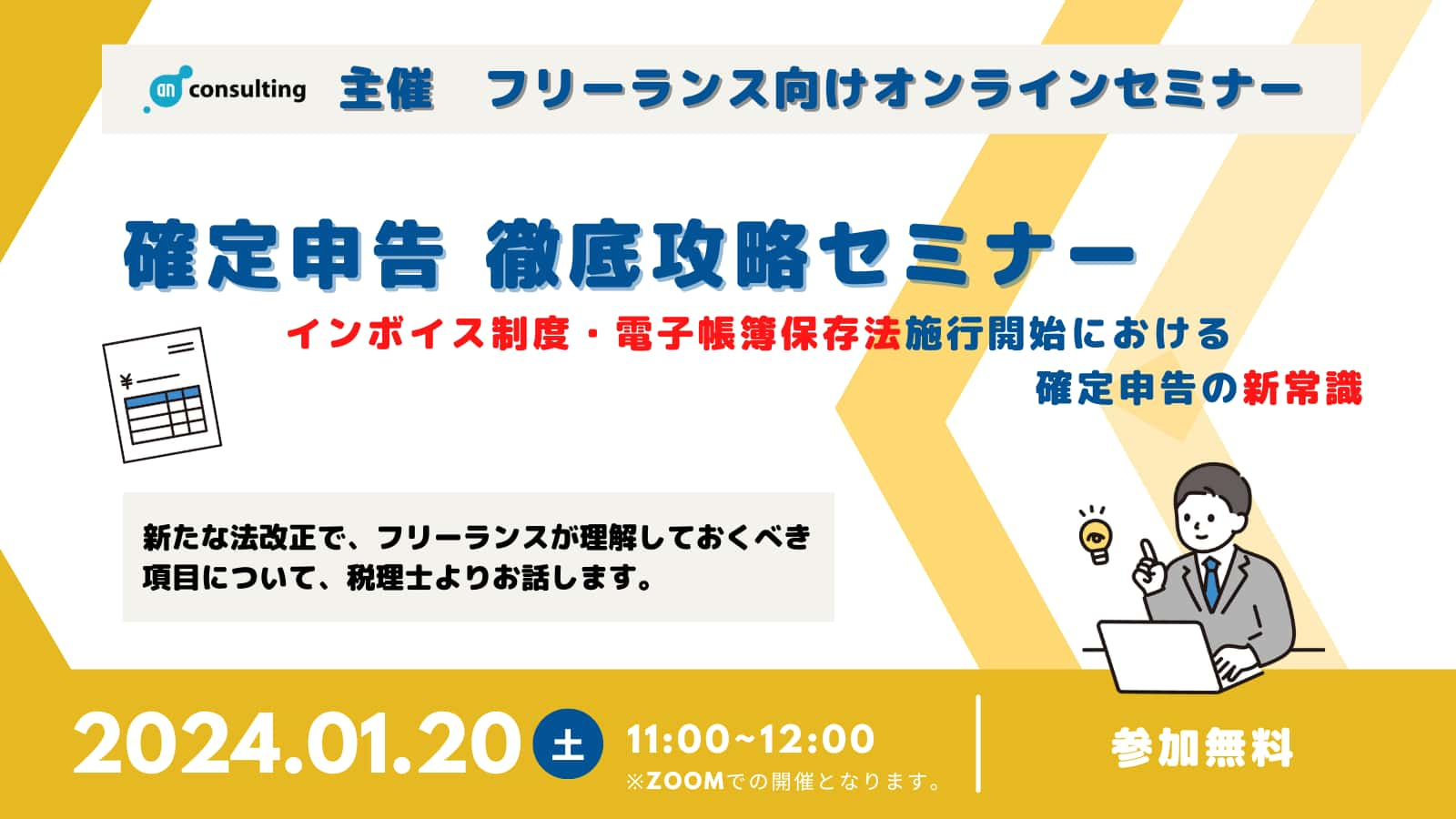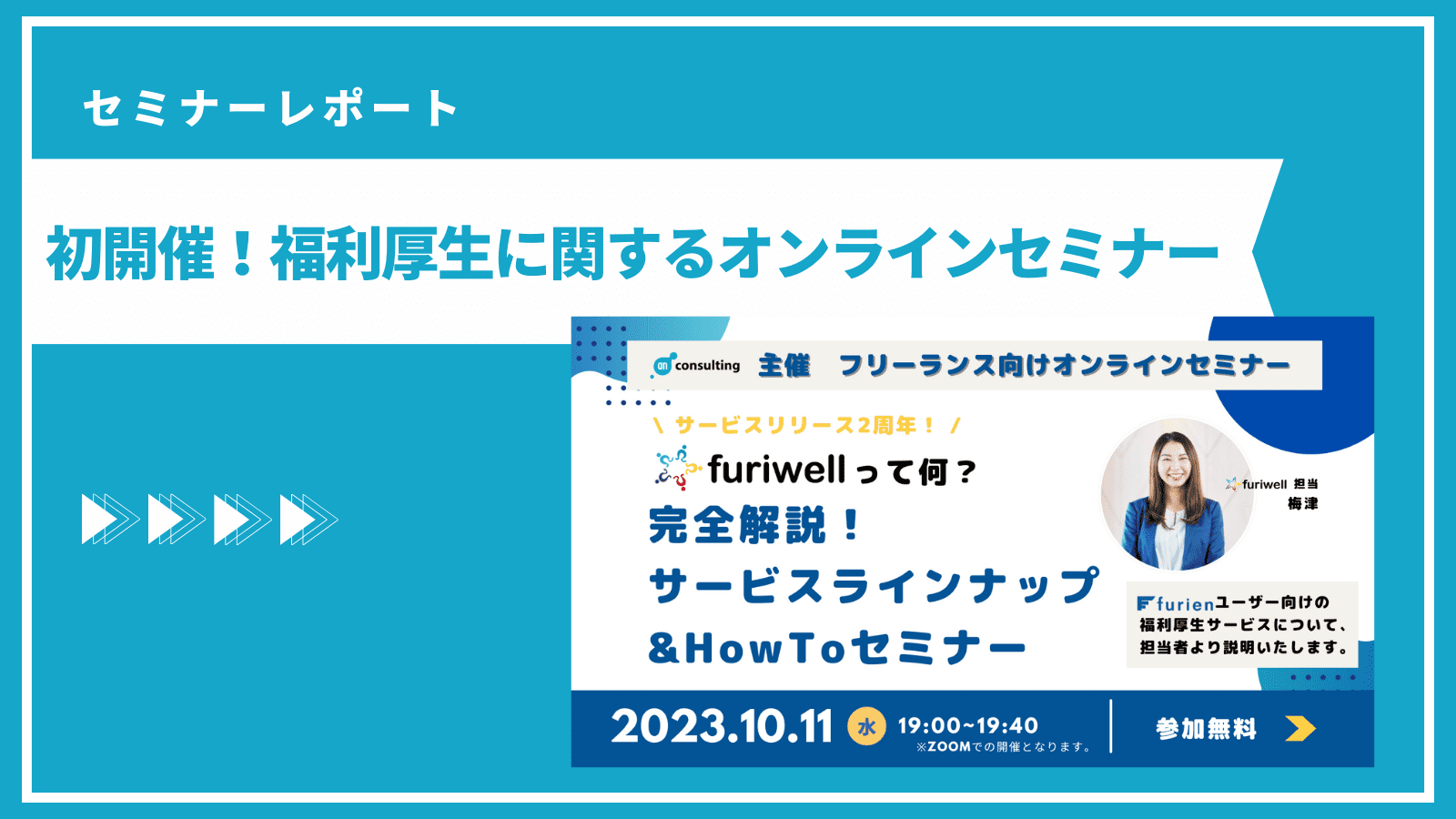新着情報






人気記事

フリーランスに聞いた【インボイス制度に関する調査】~4割以上の方がインボイス制度に不安を抱えている実態も判明~
ニュース
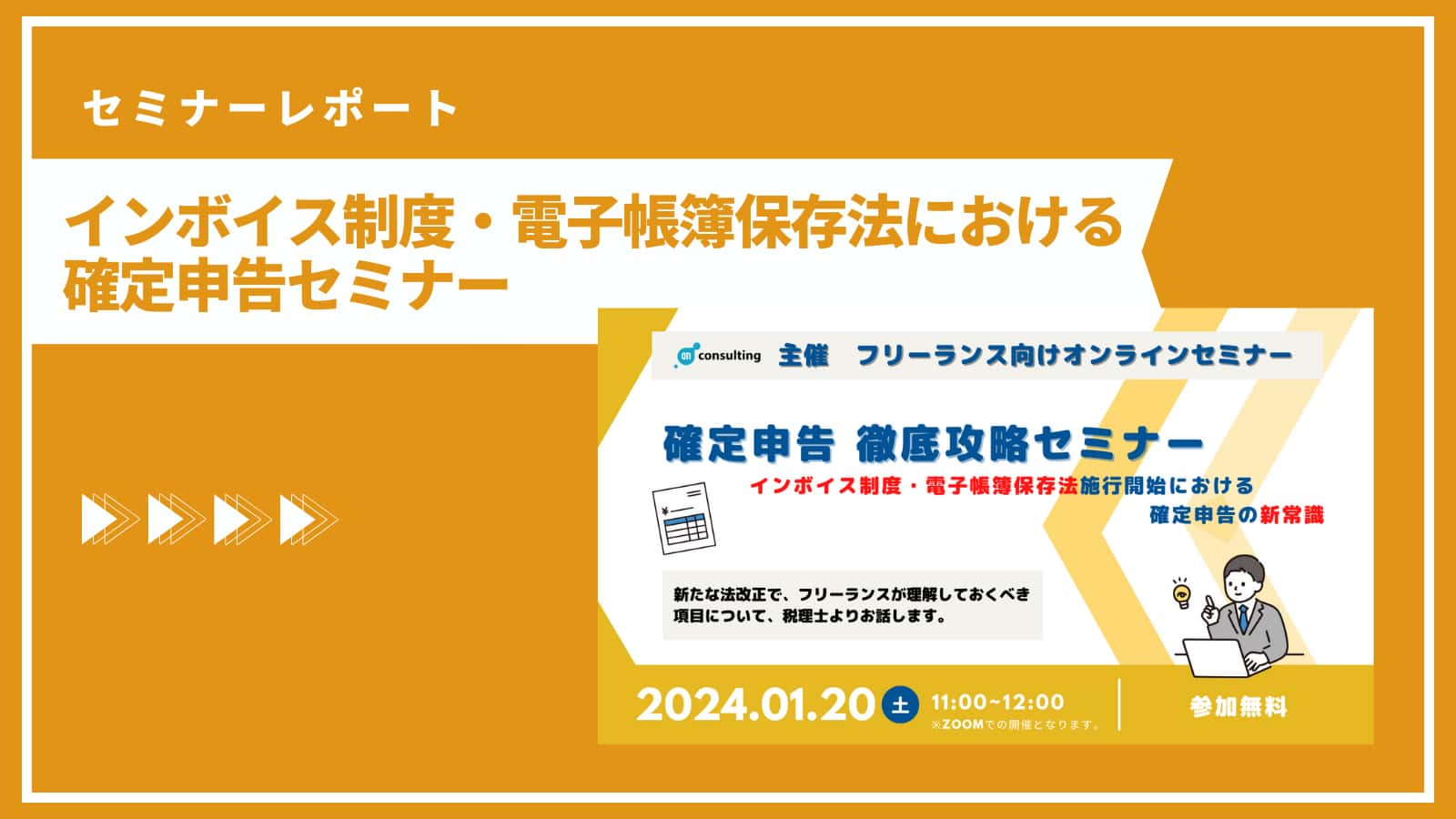
セミナーレポート【フリーランスエンジニア向け】徹底攻略!インボイス制度・電子帳簿保存法施行における確定申告の新常識セミナーを開催しました!
セミナー

【フリエン】【furiwell】が「SOKUDAN」作成のカオスマップに掲載されました
メディア掲載

【フリエン】がフリーランスメディア「フリマド」作成のカオスマップに掲載されました
メディア掲載

セミナーレポート【フリーランスエンジニア向け】税金と上手に付き合う!フリーランスのための最新資産形成セミナーを開催しました!
セミナー